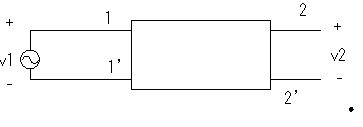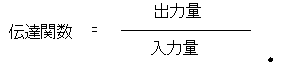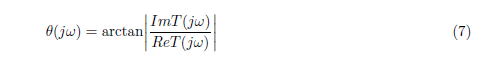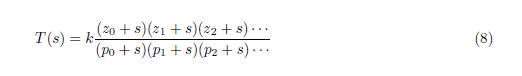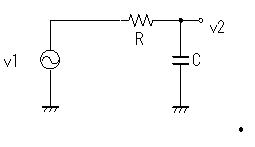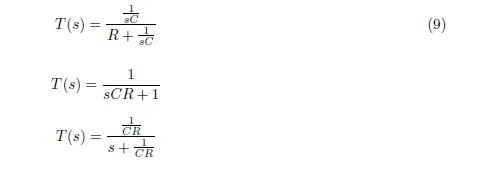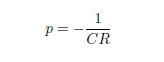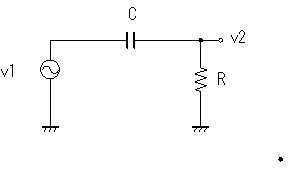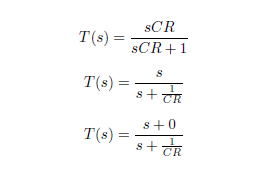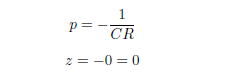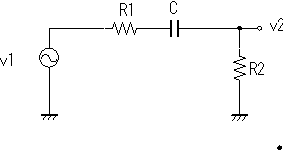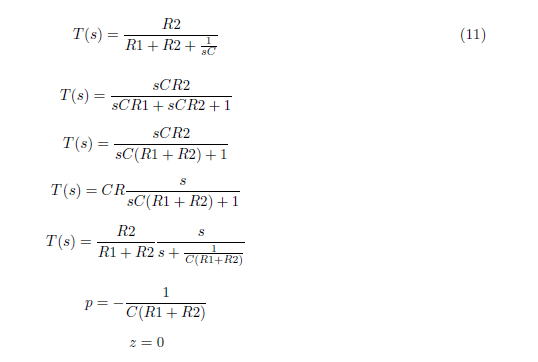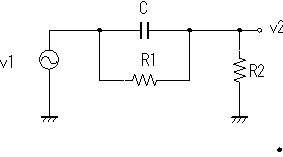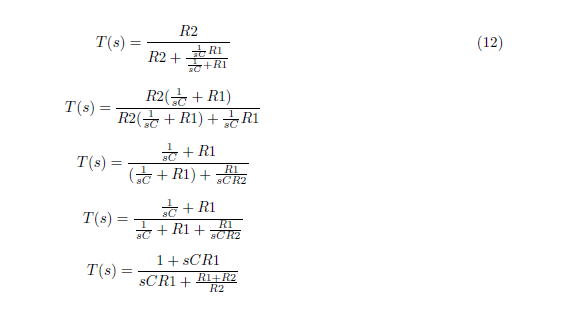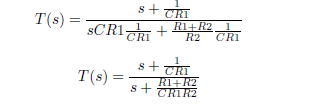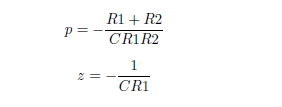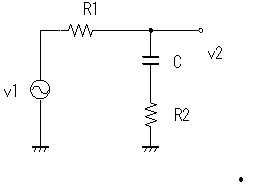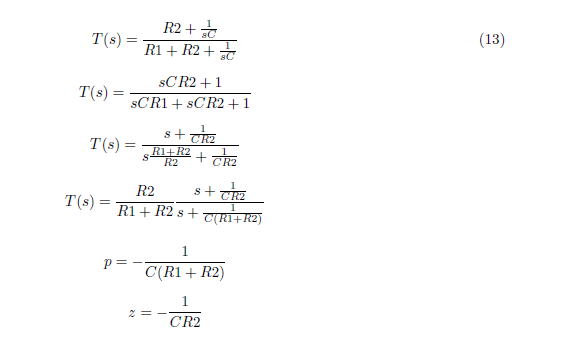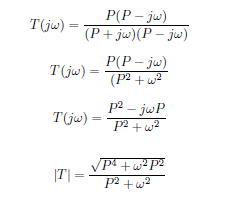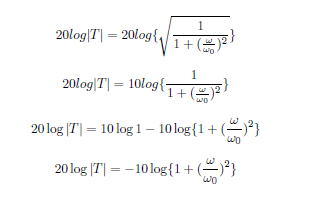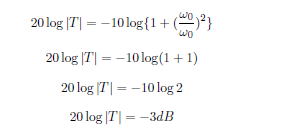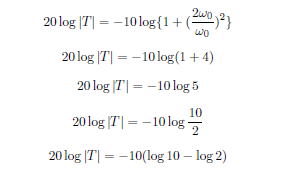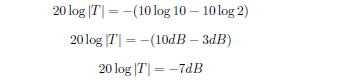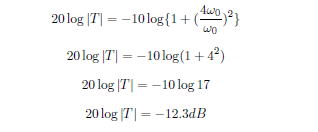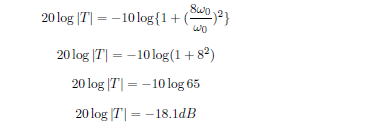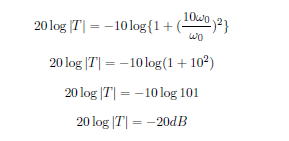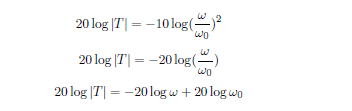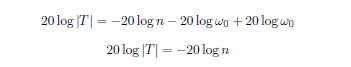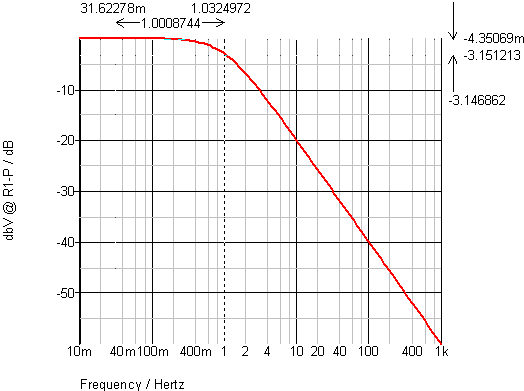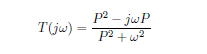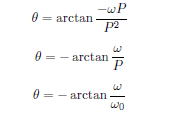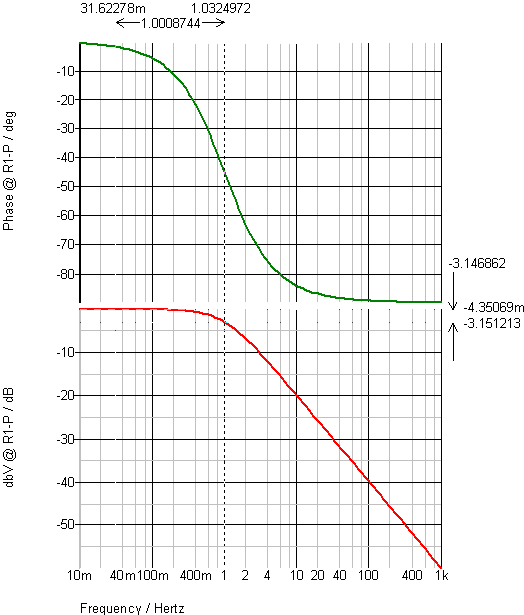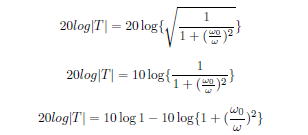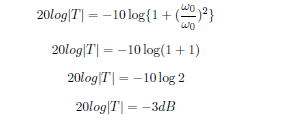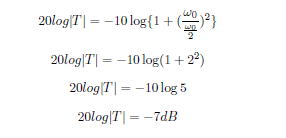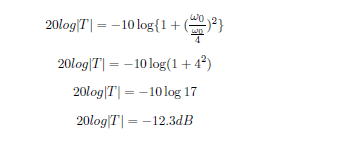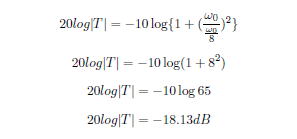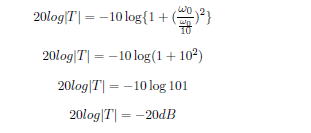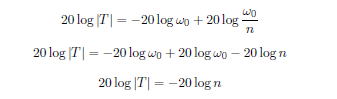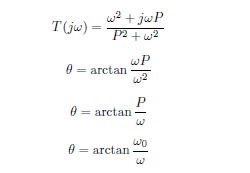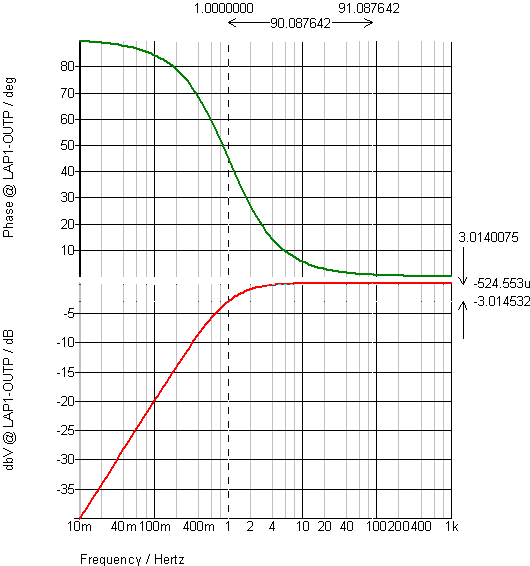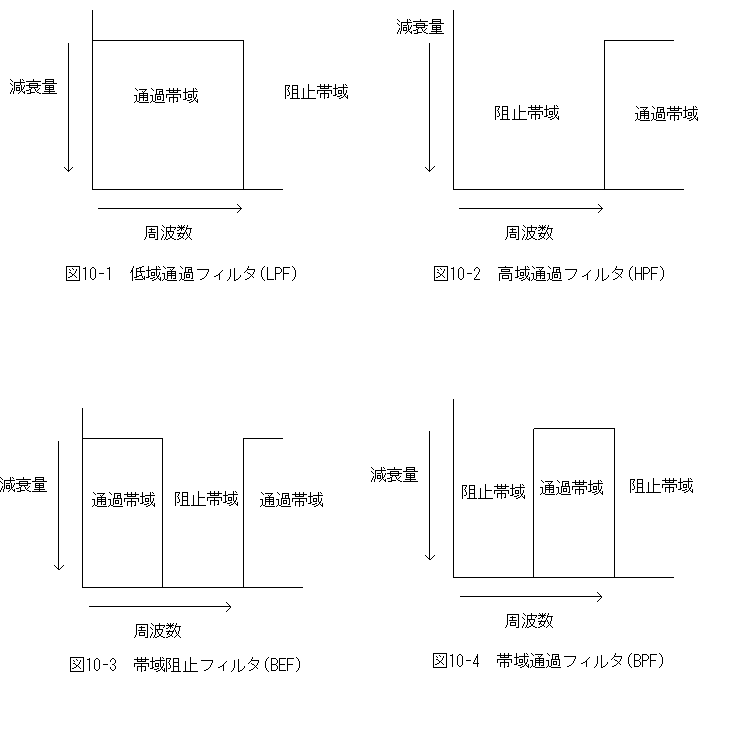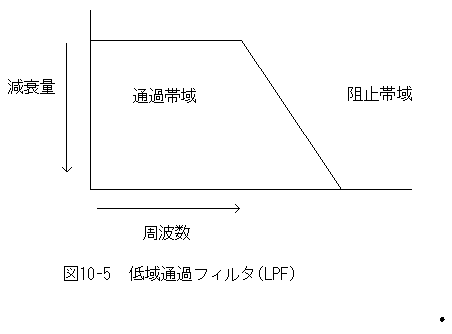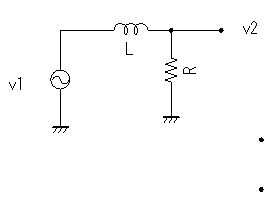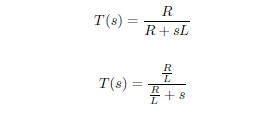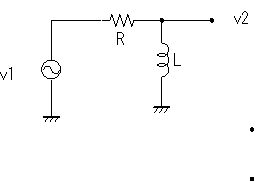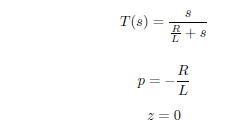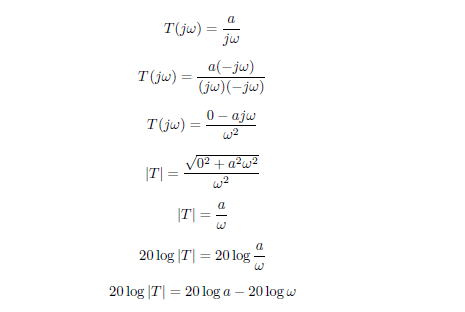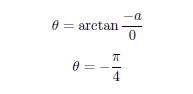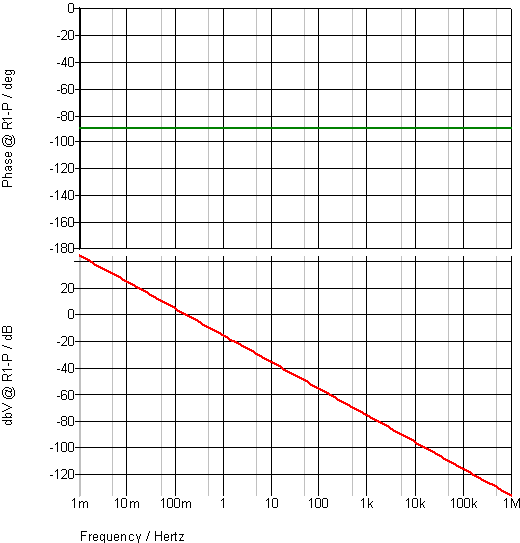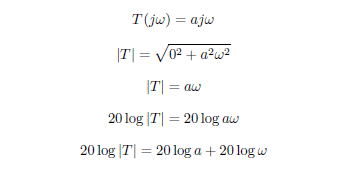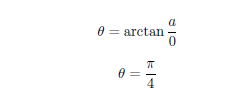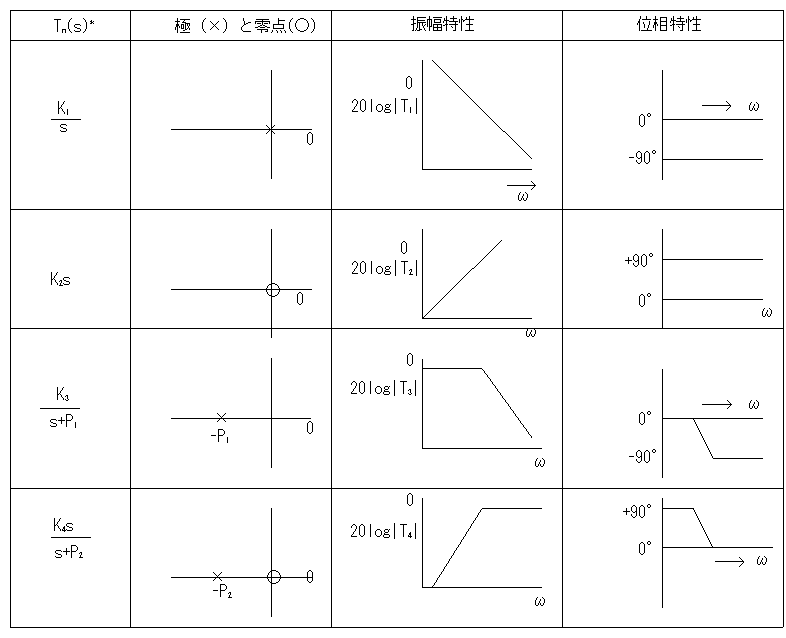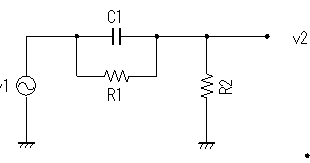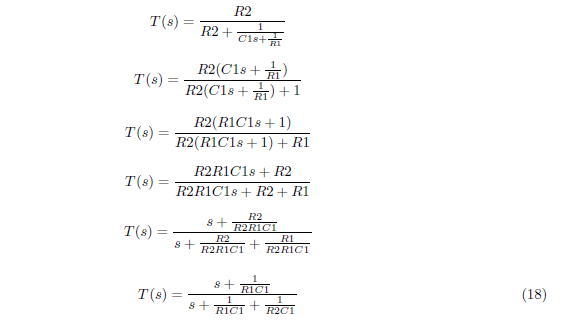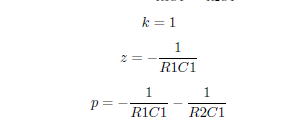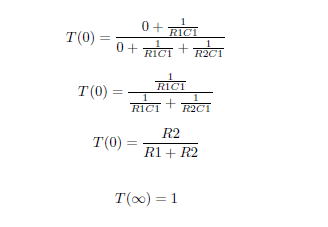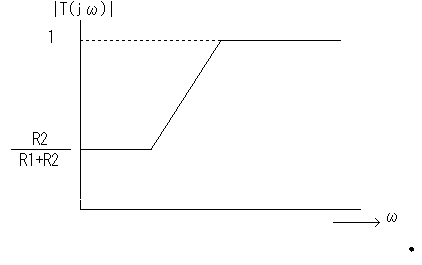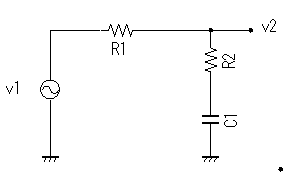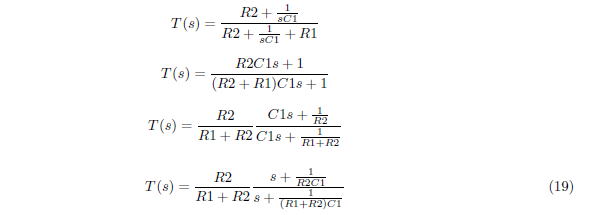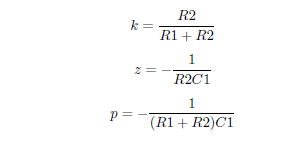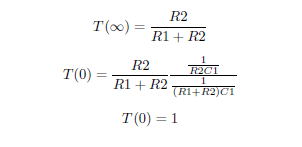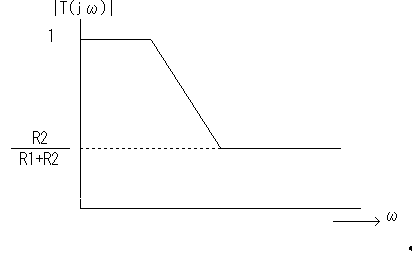フイルタの勉強
Ver.1.004 2008.10.26
更新履歴 2007. 2.12 新規作成
更新履歴 2007. 6 .8 Ver.1.001
更新履歴 2007. 6.10 Ver.1.002
更新履歴 2008.10.12 Ver.1.003
更新履歴 2008.10.26 Ver.1.004
【参考文献】
1.電機学会大学講座 電気回路論(改訂版) 電気学会 昭和50年 13版
2.電子フィルタ 回路設計ハンドブック A.B.ウイリアムズ著 加藤康雄 監訳 マグロウヒル社
3.アナログフィルタの設計 M.E.VALKENBURG著 柳沢健 監訳 金井 元 他訳 秋葉出版
4.工学基礎 ラプラス変換とZ変換 原島博・堀洋一共著 数理工学社
5.アナログフィルタの設計と解析 堀敏夫著 電波新聞社
【はじめに】
フィルタはいろんなところで利用されています。これを勉強してゆきたいと思います。
さて、以下においては,文献3の定義に従い,
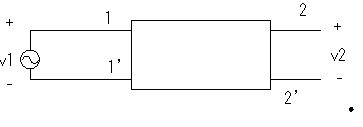
図 1.1 定義
入力端子1-1'に電圧源v1が接続されているものとします。また、v1の位相をθ1、v2の位相θ2をとします。伝達関数は、
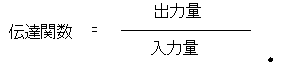
と定義します。
伝達の大きさは、

位相は、

となります。測定においては,一般的はθ1=0としますので以後はθ1=0ということです。
また、測定においては,伝達の大きさを

のようにして、Aをゲインといいます。これはdBという単位がつきます。
余談ですが、入力レベルの大きさは、基準を1mW600Ωのレベルを(0.774597Vrmsですが)0dBmとしたdBmという表記があります。
また、1Vrmsを基準としたdBVという表記もあります。
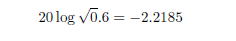
ですから、
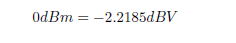
という関係があります。ですからdBm値に-2.2185を足せばdBVになります。たとえば,
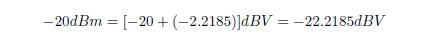
として変換できます。
さて、ここでは、正弦波定常状態を扱うので,

とします。これについては,後でふれます。
さて、Tは(4)式をつかって、複素数で表せ,極座標では
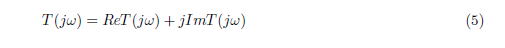
のReのついたほうを実部といい、Imのついたほうを虚部といいます。
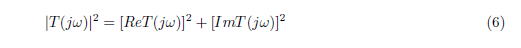
を振幅といいます。
また、
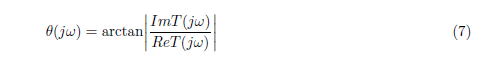
を位相といいます。
【極と零点】
Tは、
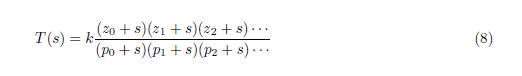
とあらすと、分子を0にするs=-z0,s=-z1などを零点と呼び,分母を0にするs=-p0,s=-p1などを極といいます。
式(8)からわかるように,極、零点ともkとは関係ありません。
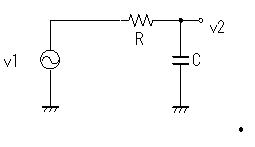
図2 CRフィルタ(LPF) その1
この回路は,
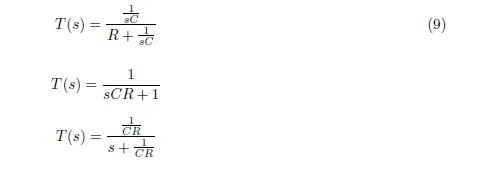
となるので,零点は無く極のみあり、
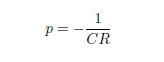
となります。
また、下の回路では,
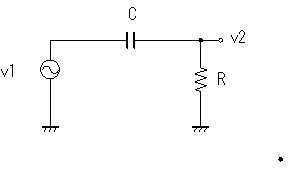
図 3 CRフィルタ(HPF) その2
この回路は、

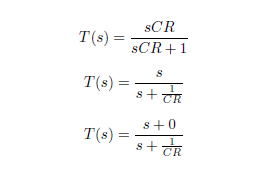
となるので、零点,極は
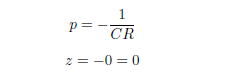
となります。
では、これはどうでしょう。
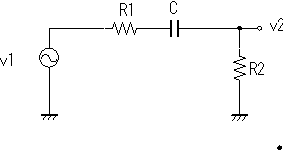
図4 CRフィルタ その3
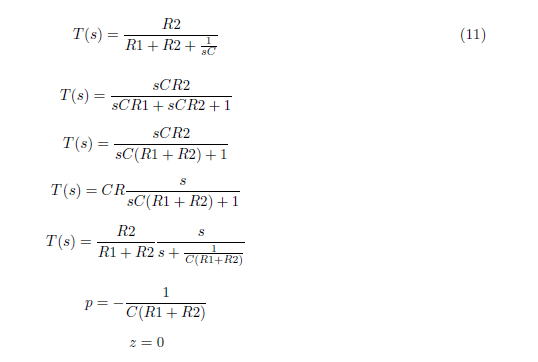
図3との違いは
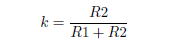
と
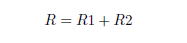
だけですね。
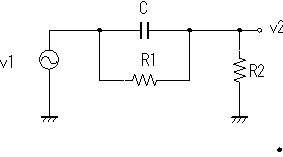
図5 CRフィルタ その4
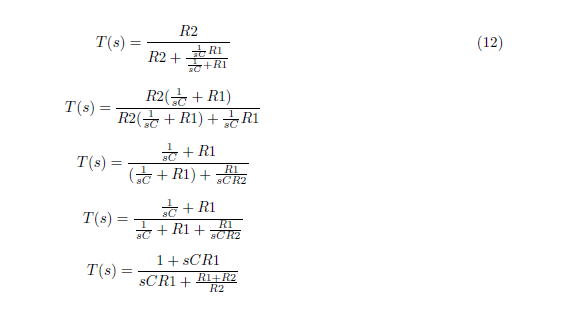
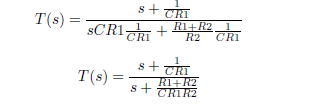
零点と極を求めると,
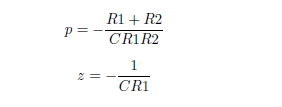
です。
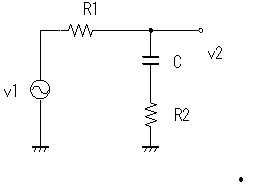
図6 CRフィルタ その5
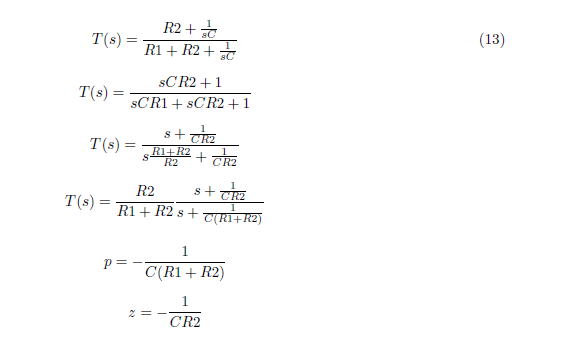
です。また、
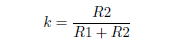
です。
以上で,零点、極の求め方がわかりました。
では、周波数特性とか位相特性はどうなっているでしょうか。
図2のLPFの場合、

という伝達関数になります。ここではPは極ではなく定数を表すものとします。
P=1/CRです。これをを見てみましょう。(4)式より、
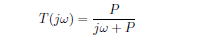
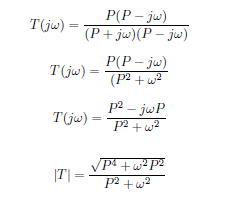
となります。ここで、
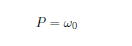
としますと、

と求まります。これをデシベルにしましょう。
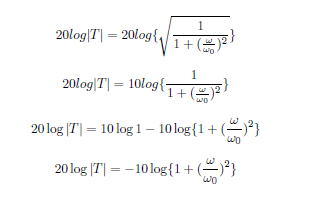
となります。いま、
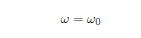
であるとすると
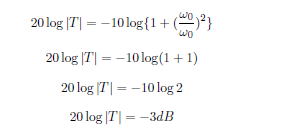
この振幅特性が-3dB落ちるところをカットオフ周波数といいます。
(6)式の実部と虚部の絶対値が均しくなる周波数です。したがって、(7)式より
|θ|=45°になります。
また、
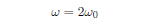
であるとすると
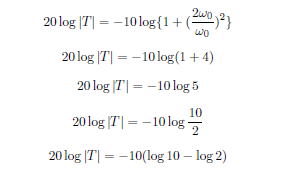
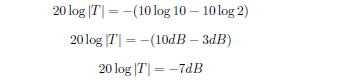
さらに、

であるとすると
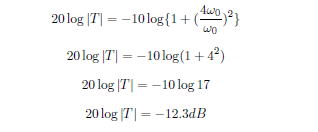
さらに、
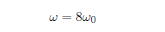
であるとすると
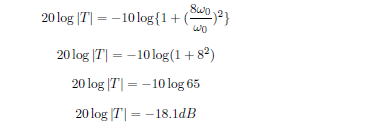
最後に、
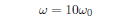
であるとすると
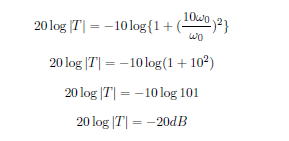
となります。
ωがさらに大きくなると次のように近似出来ます。減衰量は
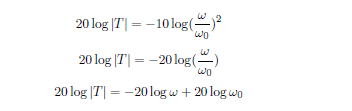
と表せ、ωに応じてどんどん大きくなります。
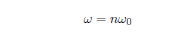
とおくと
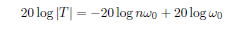
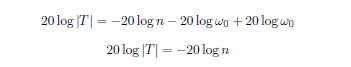
となり、n=2なら-6dB/oct、n=10なら-20dB/decとなります。
-6dB/octというのは、octave(周波数が倍になる)毎に-6dB落ちるという意味です。
-20dB/decというのは、decade(周波数が10倍になる)毎に-20dB落ちるという意味です。
これをグラフにすると
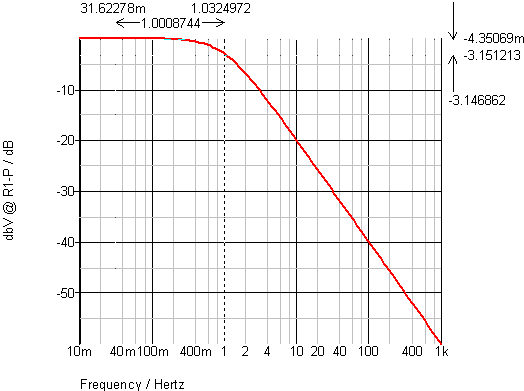
図7 |T|の特性 (ω0=1/2πのとき)
になります。数値が多少ずれています。
さて、位相は
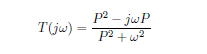
より、
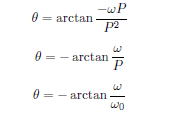
となります。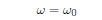 でθ=-45°になります。
でθ=-45°になります。
ωが0ならθ=0になり、ωが∞になるとθ=-90になりますね。
これをグラフにすると
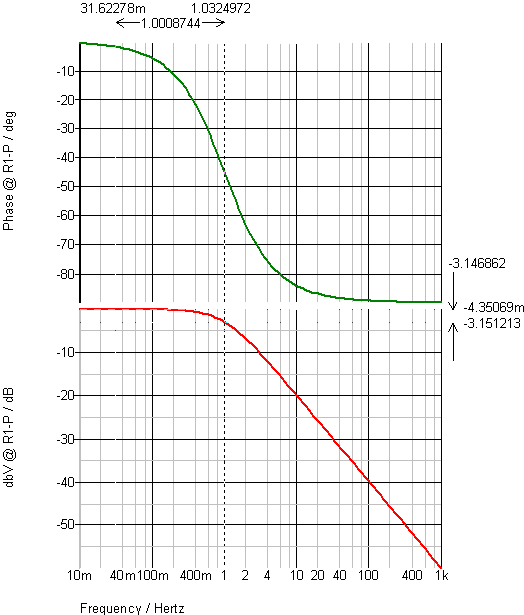
図8 位相特性(緑) 振幅特性(赤) (ω0=1/2πのとき)
となります。振幅特性の傾きは-6dB/oct(あるいは-20dB/dec)です。
では、図3のHPFの場合も見てみましょう。

となります。Pは極でなく定数でありP=1/CRです。またP=ω0とするものとします。

これをデシベルにして、
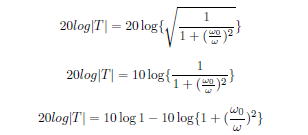
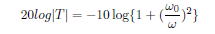
そこで、
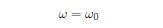
のとき、
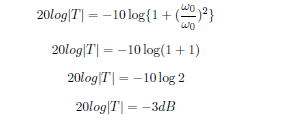
となります。これをカットオフ周波数といいます。
また、
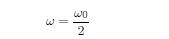
のとき、
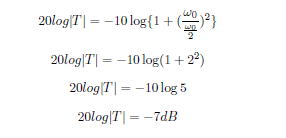
で、さらに、
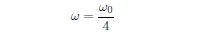
のときは
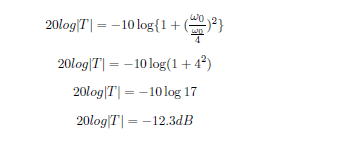
で、また、
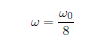
のときは、
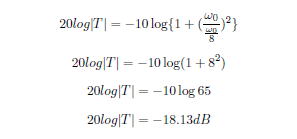
で、最後に
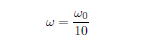
のとき、
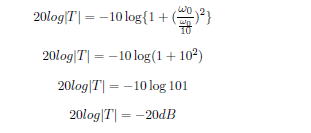
となります。さらに、ω<<ω0 になるとどうでしょうか。
そこで、
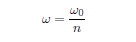
とすると ω<<ω0 ですから近似すると、
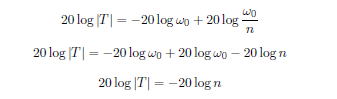
です。n=2なら-6dB/oct、n=10なら-20dB/decになります。しかし、nが大きくなると周波数が下がる方向なので
周波数が増える方向で考えると6dB/oct、20dB/decとなります。
また、位相は
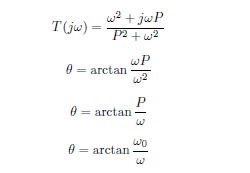
より、ω<<ω0 ではθ≒90°、ω=ω0 では45°、ω=∞では0°となります。
グラフにすると、
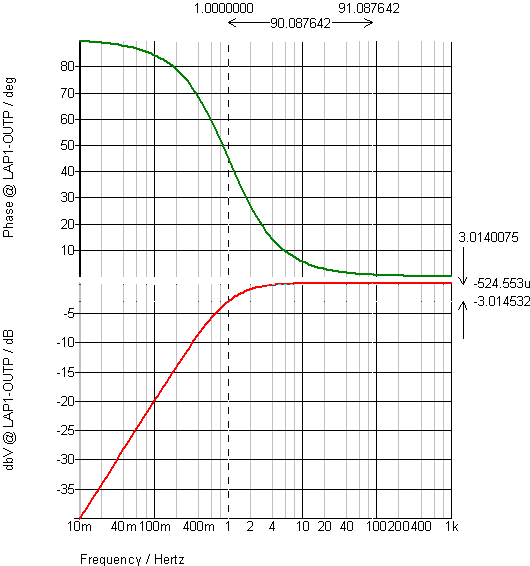
図9 位相特性(緑) 振幅特性(赤) (ω0=1/2π)
となり、ハイパスフィルタであることがわかります。振幅特性の傾きは6dB/oct(あるいは20dB/dec)です。
さて、フィルタとは、どういうものか整理してみます。
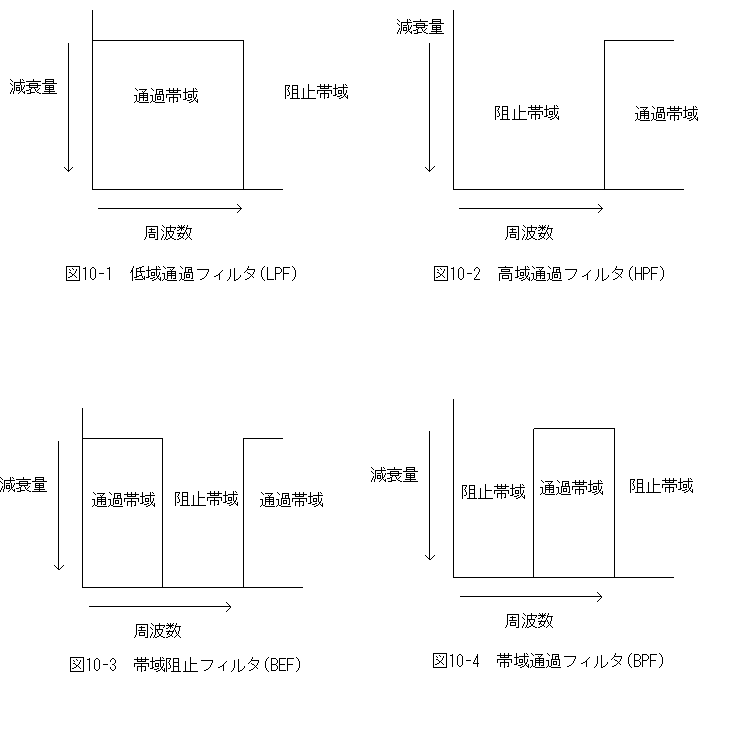
フィルタは基本的にこの4つに分けられます。阻止帯域とは、この周波数は通過を阻止するということで、通過帯域とはこの周波数は通過できるということです。
この図では、通過帯域と阻止帯域が垂直に切り分けられていますが、実際は傾斜を持ちます。
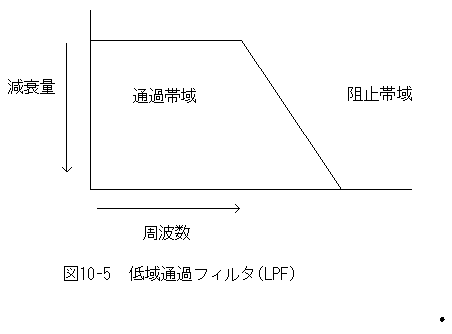
たとえば、こうなるわけです。
さて、もとに戻って
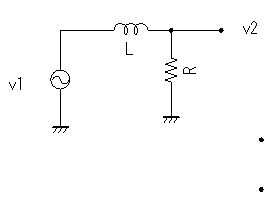
図10 LC LPF
この回路の場合、
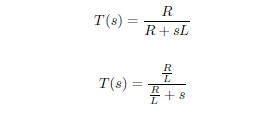
これは、既にでてきたCR LPFとおなじですね。
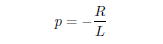
また、
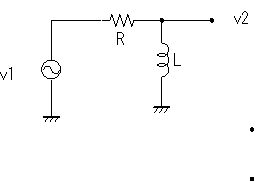
図11 LC HPF
この回路の場合、
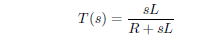
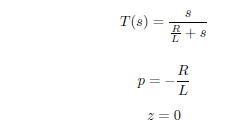
となり、これは既に出てきたCR HPFとおなじですね。
では、まだ説明のしてない一般的なs式の振る舞いについて見てみます。

この場合どうなるでしょうか。
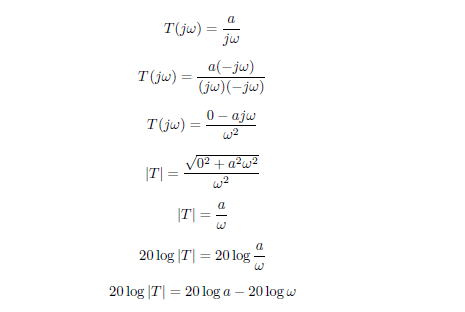
この場合、P=0ですね。ωが2倍になると-6dBづつへってゆきますね。
また位相は,
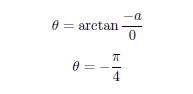
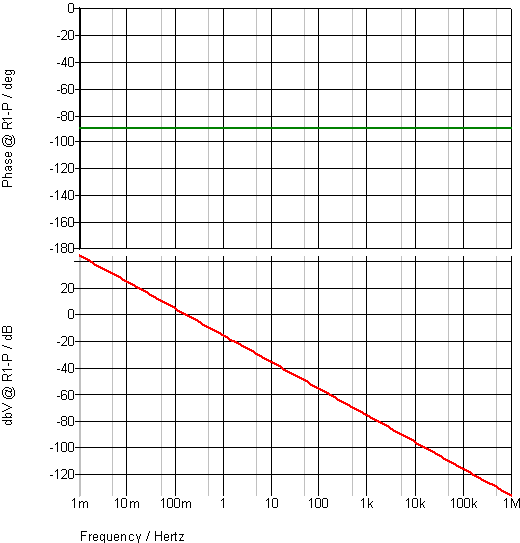
図12 T(s)=a/sの周波数特性 緑 位相特性(-90°) 赤 ゲイン特性
これは積分器の特性です。
では、

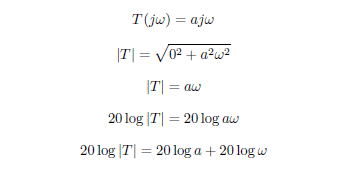
この場合、z=0です。
グラフは右上がりの直線になります。その傾きはωが2倍になると6dBづつふえてゆきますね。
位相は
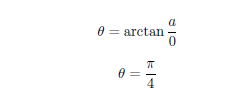
となり、90°です。
これは、微分器の特性です。
これまででてきた結果をまとめると次のようになります。
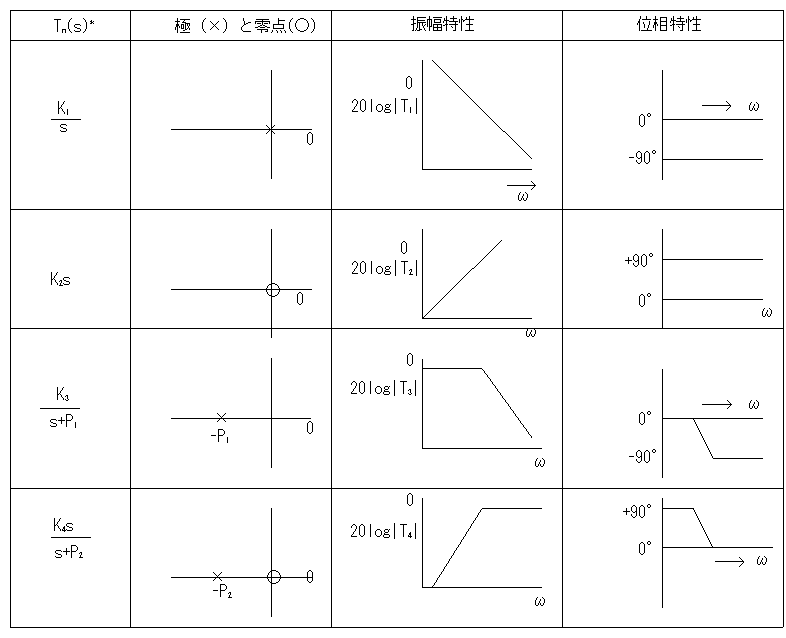
図13 ボーデ線図
さて、
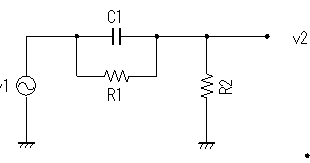
図14
この回路を見てみましょう。
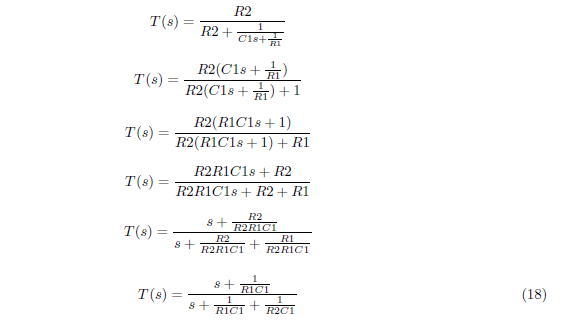
より、
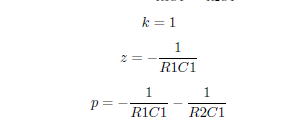
となります。ここで p < z です。
また、
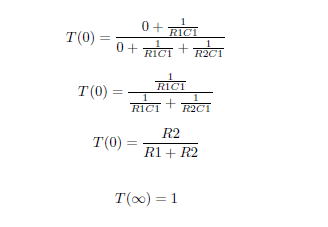
したがって、
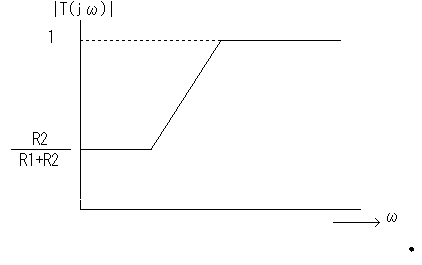
図15
となります。
では、
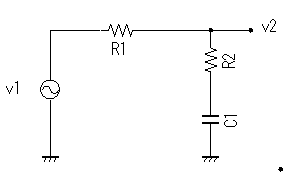
図16
この回路はどうでしょう。
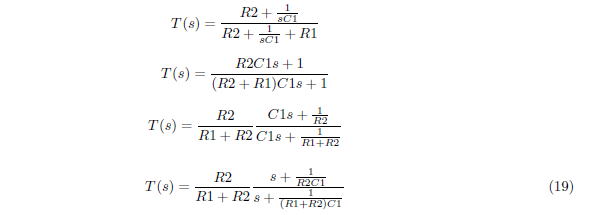
より、
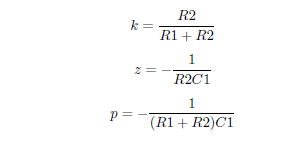
です。ここではz < pですね。
また、
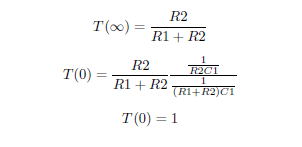
したがって、
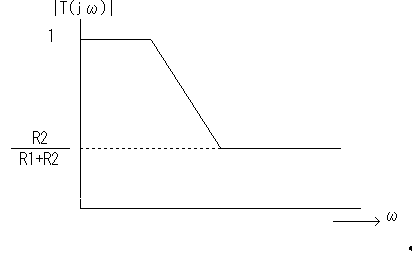
図17
となります。
この2つの回路は、
T(0),T(∞)は入れ替わっていますが、値は同じです。

と表されます。
pとzの大小関係によって、LPF的であったり、HPF的であったりします。
メインページに戻る